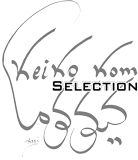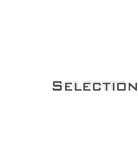京都に拠点を持つ様になり、何のきっかけか覚えていませんが、大いなる働きかけに導かれ、大津の古い会館にて「大地の声」を開催する事になりました。二階に楽屋となる会議室がありました。その部屋に入った時、私は突然部屋を出て、外階段を駆け下りたのです。通りを渡り、爽やかな香りに導かれ、湖畔の道を歩いて行ったのです。心の中で琵琶湖だと叫びながら、嬉しくて嬉しくて飛び跳ねる様にし歩いたのです。何があんなに嬉しかったのか分かりません。心はときめいてなりませんでした。そして湖畔に立ち、湖の音に心澄まし、遠い古の時を辿る様にし内面を感じました。遠い古の時にこの波の音を聞いていると感じる感覚があります。とても懐かしく愛おしい感覚です。

私はノートとペンを持ち、再び湖畔に立ちました。心澄ますと、時間を超え、次元を超えた世界が立ち現れます。この風を知っている魂を感じます。打ち寄せる波の音、心地よく吹く風、只一緒に居る事が楽しく共に歩いた湖畔の道。古の光景が心に見えるのです。月夜の道を肩を並べて歩いた時のときめき、楽しさを知っているのです。何があったのか、何処に向かっていたのか分からなくとも肩を並べて歩いたときめきは胸の内にあるのです。ノートに詩を綴り、懐かしい香りに包まれ、心ときめく幸せな時でした。楽屋に戻った時も心はときめいてなりませんでした。少し暗い古い会場で「大地の声」をしたのです。そして私は再び、どの位の月日が経ったか覚えていませんが、この会場で講演会をしたのです。前回と同じに二階の会議室が控室となっていました。前回と同じに再び部屋を出、外階段を駆け下り、通りを渡り湖畔に向かって走ったのです。只々嬉しくて湖の畔に立つのです。そして湖畔にて波の音を聞き、遠い昔の記憶を思い出す様に心澄ますのです。生まれる詩は今日も共に歩いた月夜の道、ただ一緒に居る事が楽しく、幸せだった。この幸せが永遠に続く様にと祈る様に歩いた道。けれど突然別れが訪れ、離れ離れになったのです。永遠に続くと感じた幸せな時は一瞬にし壊され、悲しみが全身を貫く別れが訪れたのです。琵琶湖の畔での「高句麗伝説」の時に、この詩を詠む時涙こみ上げます。魂の声と分かります。作り物によっては胸動き涙する事はありませんが、魂の真に触れると胸動き、涙によってより魂の悲しみ、愛は表わせない事を知るのです。泣いて詠んだ詩です。とてもロマンチックな演奏であった事は心に刻まれています。いだきしん先生は、その地の歴史、そこに生きてきた人々の状態、心の襞までもひとつとなり受け容れ、即興演奏により表現して下さいます。自分では決して表現出来ない感情、心の襞までも表現されると全ては癒され、光に包まれ、生きる力と変わるのです。私は琵琶湖の畔でのコンサート会場にて、いだきしん先生のコンサートや「高句麗伝説」を開催するようになりました。動員活動の為に講演会を開催していますが、必ず琵琶湖の畔の会場を借りるのです。どの会場を借りても窓から琵琶湖がよく見えるのです。どの会場を借りても私は通りを渡り湖畔に佇むのです。共に動くボランティア仲間達は、琵琶湖の畔での講演会が大好きです。何か心ときめき、魂震えるのです。皆で一斉に集い会場作りをし、講演会が終わるとまた一斉に片づけをし、それぞれの地に帰っていくのです。いつも琵琶湖のときめきの風が共にあります。皆心ときめきウキウキし、講演会の時を過ごすのです。このときめきは未来に何になっていくのでしょうか。魂導かれ、縁ある地へと行くのです。比叡山中腹に工房を作る巡りとなりました。始めにここであればと感じた土地は、広大な土地でありました。眼下には琵琶湖を見下ろせました。国創りの風が吹きました。私はここでなら国創りが出来るとお腹の底から生まれた気持ちがあり、比叡山の中腹に工房と家を作り、迎賓館まで作ったのです。
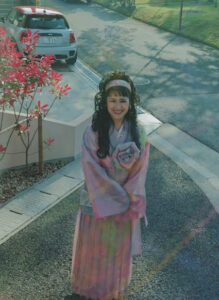
迎賓館は、いだきしん先生が表現出来るピアノを置くピアノのホールを作りたく、土地を探し続けました。日本中探しましたが、比叡山と決まったのです。国創りの風がここと教えてくれたのです。そして現実では様々な巡りにより、今作った迎賓館の土地より縁がなかったのです。他の土地は縁が出来ず、話が成立しなかったのです。今迎賓館がある土地に立った時、この地は世界に繋がっていると見えたのです。ここでの表現は世界に繋がっていくと驚喜しました。故にここでより、ここの土地しか買えなかったという事が分かりました。現実で考えれば、狭い土地で自分が計画していた広さのコンサートホールは作る事が出来ませんでした。が、ここに導かれ、作るよりない巡りとなったのでした。比叡山にお茶室も作り、4つの建物を作りました。何でこんなに縁があったのかは分からぬままに国創りの風に導かれ、作る事になったのでした。ある日、比叡山がある地は昔は近江の国と言われていた事、近江の国の国司は高麗福信さんであった事を初めて知りました。その時、比叡山に4つも建物を作った事の意味が分かり、深く合点が行ったのです。縁あってこの地で国創りをしていくのだという事が見えました。